スタッフブログ
〜日々の活動を発信しています。〜
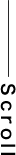
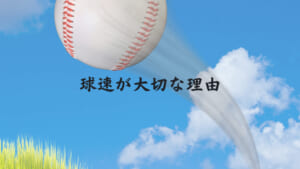
球速が大切な理由
こんにちは! 1st Triggerの山﨑です! 当店に通われている選手の 最も多い要望は「球速アップ」です。 このオフもみっちりトレーニングを頑張ってくれた選手の中には、 約20kmほど球速が上がった選手もいました。 しかし、中には球速は追い求めておらず、 コントロールや変化球を駆使して技巧派で勝負したい。 こんな投手もいます。

第2期中3塾終了!
こんにちは! 1st Triggerの山﨑です! 3月をもちまして第2期中3塾の全日程が終了いたしました! 毎週店舗に来ていただいて、 身体を追い込む選手たちにを尊敬しています。 また、遠方から毎週送迎をして下さる親御さん達にも 非常に感謝しております。 改めまして、 第2期中3塾に参加していただいた選手・保護者の方々へ感謝いたします。 約半年間ありがとうございました!!

料金変更と会員制導入のお知らせ
こんにちは! 1st Triggerの山﨑です! 今回は重要なお知らせです。 料金変更と会員制導入 4月から学割を廃止し、会員/非会員価格でサービスを提供いたします。 会員の方は様々な特典を受けることが出来ます。 ✅ トレーニング料金割引 パーソナルトレーニング料金 60分 8,000円 ⇒
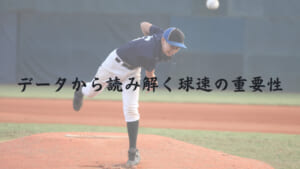
データから読み解く球速の重要性
こんにちは! 1st Triggerの山﨑です! ピッチャーのほとんどが、 「今より速い球を投げたい!」 という希望があると思います。 当店でも最も多い要望が この「球速アップ」です。 それでは、 なぜ球が速い方が良いのでしょうか? 結論、

失点のリスクを減らすには?異なる2つの投手像
こんにちは! 1st Triggerの山﨑です! 投手は全員が失点したくないと考えていると思います。 試合に勝つために点をあげる投手はいませんよね? では、どうすれば失点のリスクを最小限にすることが出来るでしょうか? 最も大切なのは以前の記事に書いた 奪三振・与四死球・被本塁打数の指標を上げる事です。 ⇧ 以前の記事はこちら 失点の70%はこれらの数値が関わってきます。 そこで、残りの30%は何でしょうか?
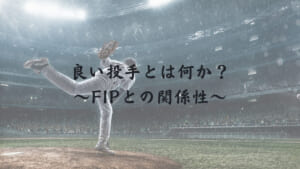
良い投手とは何か?~FIPとの関係性~
こんにちは! 1st Triggerの山﨑です! 野球の勝敗に大きく関わるのが投手です。 どのカテゴリーでも投手が良いチームはそれなりの所まで勝ち上がります。 しかし、良い投手とはどんな投手でしょうか? 具体的の言語化できますか? 野球のタイトルは、 ・最多勝 ・最優秀防御率 ・最高勝率 ・奪三振王 などありますが、

低周波治療器導入
こんにちは! 1st Triggerの山﨑です! 今月より店舗にて『低周波治療器』を使用できるようになりました! 低周波治療器とは、微弱な電流を皮膚表面に流し、神経や筋肉の緊張を緩和させることが出来る機械です! 主な効果は、 ✅ 痛みの緩和 ✅ 疲労回復 ✅ 血行促進 ✅

フィジカルチェックシート配布中
こんにちは! 1st Triggerの山﨑です! 11月中旬から選手に自分の身体の状態がわかるように フィジカルチェックシートを配布しています。 今までは僕がパソコンで選手のデータを 記録していたのですが、 選手自身が長所や短所を把握できるようにしました。 測定項目は様々ですが、 ・Inbodyによる体組成結果 ・瞬発力 ・柔軟性

Inbody常設してます!
こんにちは! 1st Triggerの山﨑です! 12月下旬にInbodyという体組成機器を導入しました! こちらのInbodyは、 体重や体脂肪率だけでなく ・徐脂肪体重 ・徐脂肪指数 ・各部位の周囲長 など、
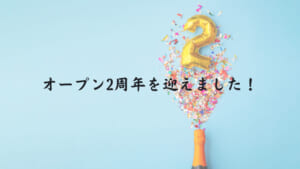
オープン2周年を迎えました!
皆様あけましておめでとうございます! 本年もよろしくお願いいたします! 1st Triggerは本日1/4から営業を再開しております! そして本日1/4で1st Triggerはオープン2周年を迎えました。 これも選手や保護者の皆様に支えられた結果だと思っています。 本当にありがとうございました。 今年も様々な挑戦をしたり、新たなサービスを提供していきます。
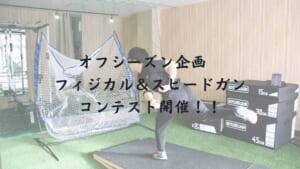
オフシーズン企画 フィジカル&スピードガンコンテスト開催!!
こんにちは! 1st Triggerの山﨑です! 11月から3月にかけて 「フィジカル&スピードガンコンテスト」 を開催いたします! ルール 11月~3月にかけて測定した各項目の 伸び幅を競っていただきます! 測定項目は、

秋季大会とドラフト会議
こんにちは! 1st Triggerの山﨑です! 10月も下旬となり、 秋季北海道高等学校野球大会・2023年ドラフト会議が 終了いたしました! シーズンもひとまず一区切りとなり、 オフシーズンに入った方が多いのではないでしょうか? 秋季大会 初開催となった札幌ドームでの高等学校野球大会。 今年は「北海高校」が優勝となりました。

高校野球秋季大会 初の札幌ドーム開催を観戦
こんにちは! 1st Triggerの山﨑です! 先日、初開催となる 札幌ドームでの高校野球の大会を観戦してきました! 優勝すると春の甲子園が当確となる重要な大会。 昨年から関わっている選手や最近関わり始めた選手たちが 出場することもあり、現地で観戦してきました! 現地に着き感じたことは、 「札幌ドームで高校野球って新鮮だな!」

まずはやってみよう!
こんにちは! 1st Triggerの山﨑です! 最近は小さな喜びがいくつかあるのですが、 そのうちの1つ。 観葉植物の新芽が次々と出てていること! 最初いただいたと比べると かなり成長しています。⇩ 左:2年前 右:現在
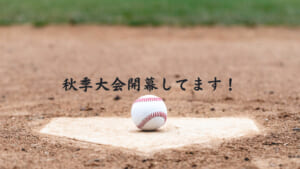
秋季大会開幕してます!
こんにちは! 1st Triggerの山﨑です! 既に開幕して数日経ちますが、 北海道高校野球秋季大会が始まっています! 新チームとなりシードも無く 完全にリセットされた大会です。 シードが無い分、強豪校が固まっている支部もあるとかないとか。 先日の試合で当店に来店されている選手が投げ合う試合がありました!

独立リーグ初観戦
こんにちは! 1st Trigger代表の山﨑です! 先日北海道独立リーグの試合を観戦してきました! 昨年は球団とパートナー契約をしていただいたにも関わらず 一度も生観戦できなかった独立リーグ。 (行く予定の日は雨で試合が行われず。。。) 今年は昨年より多くの独立リーグの選手の 関わらせていただいたので、 なんとか1度は行こうと考えていました。 そして、

パフォーマンスアップに必要な考え方 ~モビリティ編~
こんにちは! 1st Trigger代表の山﨑です! 野球のパフォーマンスアップに必要な考え方を 簡単にご紹介いたします! 今回は「モビリティ」です! モビリティとは、 筋肉の柔軟性や関節の可動性 また、関節を正しいポジションで 扱えているかの能力です。

パフォーマンスアップに必要な考え方 ~メカニクス編~
こんにちは! 1st Trigger代表の山﨑です! 野球のパフォーマンスアップに必要な考え方を 簡単にご紹介いたします! 今回は「メカニクス」です! メカニクスとは、 投球・打撃フォームの効率性のこと。 一流選手ほど優れたメカニクスでプレーしています。

パフォーマンスアップに必要な考え方 ~ストレングス編~
こんにちは! 1st Trigger代表の山﨑です! 野球のパフォーマンスアップに必要な考え方を 簡単にご紹介いたします! 今回は「ストレングス」です! ストレングスとは、 最大筋力やパワー、瞬発力、徐脂肪体重など フィジカル面の強さの事を指します。 多くの野球選手は、
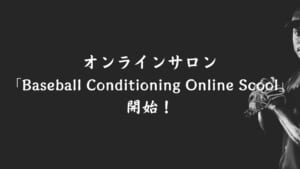
オンラインサロン「Baseball Conditioning Online Scool」開始!
こんにちは! 1st Triggerの山﨑です! この度 1st Triggerでは 新事業としてオンラインサロンを開始いたします。 野球のコンディショニングに特化したオンラインサロンです。 今回はオンラインサロン立ち上げの経緯と コンテンツについてご説明させていただきます!
copy right©️ 2021 1st trigger

